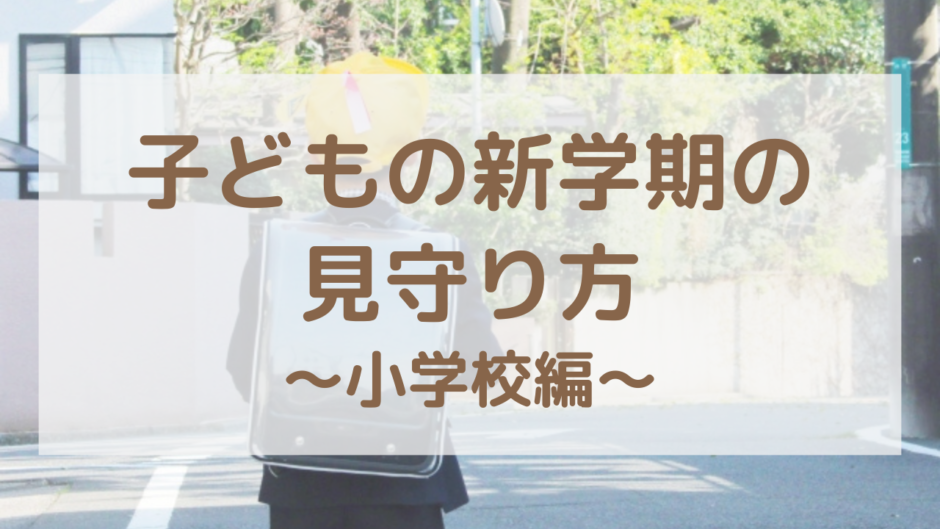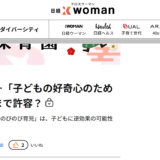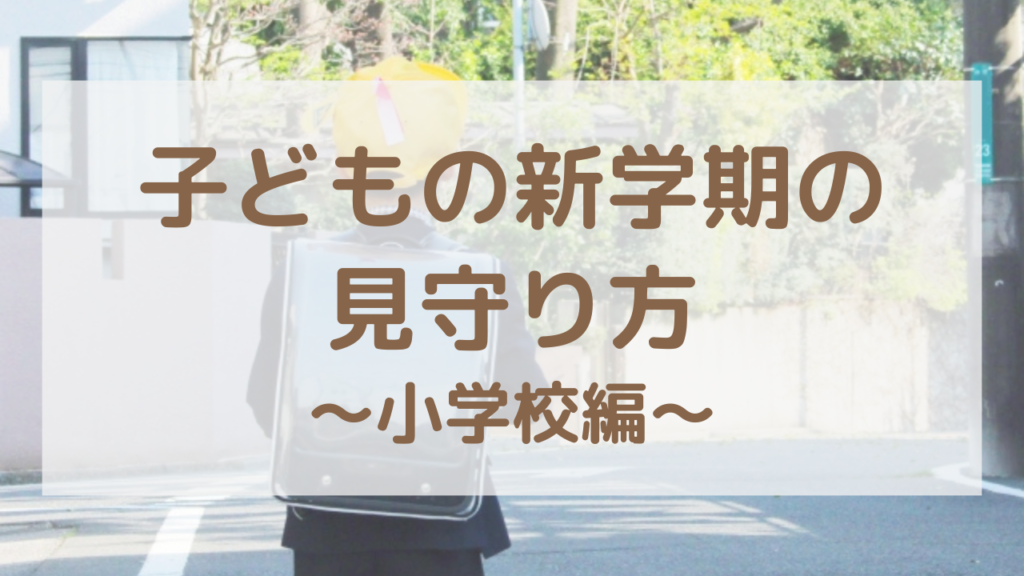
こんばんは。
カウンセラーの三条まいです。
今日は
子どもの新学期どう見守る?
をテーマに、
小学校のお話をしたいなと思います。
小学校入学を控えていたり、
子どもが「学校行きたくない」って言って
泣き出しちゃって困っていたりする
お父さん、お母さんに向けて、
「子どもの新学期をどう見守るか」
今回は特に4月・5月・6月についてお話しします。
今回の話を頭に入れておくと
新学期になった時に慌てずに、子どもを温かく見守りながら
対応できるようになると思います。
※記事の最後に動画もありますので、動画で見たい方はそちらをご覧ください
もくじ
新学期によくあるトラブルについて
『子どもが新学期に入ってどんなことあるのか』
っていうことを
最初にお話ししようと思います。
学校でよくあることっていうのは
お母さん方にとったら初めてなので
動揺することもあると思います。
先生たちや、わたしのようなスクールカウンセラーにとっても
「これってよくあるよね」みたいなトラブルは
結構あります。
「よくあることなんだ」、と知っておくだけで、
慌てずに対応できると思うので、
そのことをちょっとお話ししたいなと思います。

特に小学校入学は、
保育園に入るっていうのと小学校に入るだったら
小学校入学の方が心理的ハードルが高いかなと思います。
保育園とか幼稚園は、
明らかに先生の数も多いし
先生がすごく見守ってる体制になっていることが多いです。
でも、小学校になると、
今30人以下学級だったり、
1年生だと25人ぐらい28人とかで
その中で学級があって
対して大人一人です。
見守る大人の人数がすごい少ないですよね。
あと小学校は教育的なことをする場所なので、
小学校は
やっぱり保育園とか幼稚園と比べて
ずいぶんと親もすごい大変になるなっていうのを
すごく思います。
今回は、
特に低学年の子どもの新学期について
お話をさせていただきたいなと思います。
新学期に知っておいて欲しいこと
新しいクラス、
新しい先生、
新しいノートや教科書、
新入学の1年生は
やる気に満ち溢れてる子が本当に多いです。
1年生~6年生も、
基本的には最初は「がんばろう」みたいな気持ちに
なってる子ってすごい多いですね。
特に1年生は顕著です。
子どもによっては
「行きたくない」と泣き出すことも多くて、
これは結構よくあることです。
1年生でも2年生でもあるし、
3年生でもあったりします。
それが4月に起きる要因の代表的なものが
『母子分離不安』
と呼ばれるものです。
学年に一人か二人はそういうことが起きる、という感じです。

授業入る前にわーんと大泣きする子どももいますし、
一週間はがんばって行ってたのに、
急に4月末ぐらいから泣き出すっていう子も
いたりしますし、
ゴールデンウィーク明けてから泣き出すとか、
急に教室前でわーんって泣いたりする子もいます。
それが1年生で起きることが多いんですけれども、
2年生とか3年生になって泣く
というパターンも結構あります。
一般的にそれがよくあることなんですけれども
親御さんにすると初めてなので
「うちの子って学校でいじめられてるんじゃないか」
とかすごい不安に思ったり、
本当に激しく泣く子、
ちょっと赤ちゃん返りしたみたいに泣くというか
「こんな大きいのにこんなに泣くの?」
みたいなふうに泣く子がいるので、
親御さんもすごい動揺しますよね。
そこで「学校行きたくない」とか
すごく悲壮感漂わせて泣くことが多いので
「このまま学校に行かせない方がいいんだろうか」
って思われる方もいます。
特性がすごくあり、
どうも学校の勉強に全然ついていけないようだとか
他に主だった原因が見つかる、
そういうことでなければ、
多少学校にははげまして連れていく方がおススメです。
子どもは学校を楽しみにしてくれていることが多いですし、
お友達がいたり、遊んだりできます。
慣れてくると1週間から2週間程度で
その後けろっと通えることになることが多いので
深刻に受け止め過ぎずに学校に行った方がいいかな
と思います。

新学期の子どもの見守るために親ができること
クラス替えとかすごく緊張するので
子どもも大人も、
4月はすっごくがんばる人が多いです。
その反動で、
5月・6月に、
学校に行きたくないとか
泣き出す子も多くなったりとかするので、
プロセスを見守って褒めていくこと
が大切です。
「努力してるんだね」とか
「コツコツやってるね」みたいなことを声掛けして、
うまくいかなくなってもいい
っていう余地を残してあげる
ことが必要かなと思います。
今は大抵、
1年・2年・3年全部クラス替えあるかなと思いますが、
中学校も毎年あったりします。
高校もあるかな。
だから大変なんです、4月5月6月って。
4月は、先生の方も
赴任したばっかりだったりします。
先生達同士もなかなか新年度は大変で、
4月1日に先生来てるのに
7日とかに始業式とか入学式あったりするので、
学校内は結構バタバタしている感じがします。

西日本の話になりますが、
西日本だと最近
6月に運動会やることが多いです。
10月だと
熱中症とか9月に練習させるのが
心配だということで、
6月ぐらいに運動会やることが多いのですが、
それが逆に新年度のしんどさを
助長しているように思えます。
特に高知はとにかく暑いので
もう5月ぐらいから川に入れたり、
海に入れたりします。
そんな中で、不規則に運動会の練習が入ると、
途端に「学校に行きたくない」みたいな子が
どんどん増えていくのは
なんとかして欲しいなと
私はいつも思うばかりです。
5月6月は、
学校行きたくないっていう子が
増えることが多いです。

それは特に環境変化が苦手な子、
そこにストレスがかかりやすい子
っていうのがいて、
自分のお子さんがどのタイプかなと
見てもらえたらと思います。
環境変化にすごい疲れやすい子は
特に6月運動会とかある時期に、
今日は体育があるはずだったのに
また運動会の練習があるとか
そういう変更が多くなるとすごく疲れちゃうし
嫌になってしまうことがあります。
みんなでわーってなってるところが
楽しい子もいるし、
そこで「あー疲れたもうヤダ」ってなる子も
たくさんいます。
たぶん私もそっち派だったと思います。
みんなでわーみたいなのが
あんまり得意じゃなかった
というのがあります。
4・5・6月の流れについてお話ししました。
5月病という言葉もありますが、
子どももやっぱり
5月以降に学校行きたくないという子も増えてくるので
そのあたりゆっくり見守っていきながら、
「自分の子どもってどんなタイプかな」
というところを
見てもらえたら嬉しいなと思います、
「学校に行きたくない」原因は、お勉強のことも
もう一つ原因となるのが、
忘れちゃいけないお勉強のことです。
1年生の1学期は結構遊び要素が多くて、
学校探検だったり、
給食室がどこだとか図書室がどこだよとか
まずそこから始まったりとかします。
引き算とか足し算はほとんどやらなくて、
ひらがなをまずゆっくり書こうみたいな感じで、
割と楽しくやれる内容です。
でも、勉強ができる子は
「楽しくない」「つまらない」
ということが起きたりします。

2学期以降に勉強が始まるので
お勉強につまずくとしたら2学期からかな、
という感じがします。
よく親御さんとかで
「1学期は楽しげに行ってたのに
2学期になって急に…」なんてことがあります。
その場合、
お勉強がちょっとしんどい子は
それが起こる可能性はありますね。
1学期は割と粘土で遊んだりとか、
塗り絵したりとか、
割と楽しいことをいっぱいできるんですけど、
1年生2学期ぐらいから
結構勉強要素が増えて苦しい、
2年生になったら、
ますます九九とかあったり、
足し算も二桁になったり、。
繰り上がったりしてくるので
お勉強に苦手意識が強い子は
ちょっとしんどくなってくる
ことがあります。
1年生には問題なかったけど
2年生になって急に問題が出る
というパターンもあって、
お勉強も結構無視できない要素かな
と思います。

3年生になってくると漢字も
日曜日の曜とか
画数が多い字が増えます。
1年生の頃は日曜日の日とか
画数的には5画6画位までなのですが、
3年生ぐらいになると画数すごい増えたりとか
足し算引き算も3桁になるのかな、
3年生になったら。
なので、
代数計算あまり好きではないとか
繰り上がりでつまづいていると
3桁になった途端に
もうお手上げみたいなことになることがあります。
なので勉強がどの程度できる子か
ということも
ぜひ見て欲しいなと思います。
「学校に行きたくない」という子の
結構な割合で
勉強がすごい苦手な子多いです。
勉強できないっていうのは
すごく子ども達みんなの自己肯定感を下げてしまいます。
私はこのことをすごく心苦しいなと
いつも思っています。
本当にこれをやらなくてはいけないのか、
やらないと社会に出れないのかと言われると
そうではないことがたくさんあります。
でも、学校だと
勉強ができないと少し困ってしまうし、
できてないってわかってしまうので
それが子ども達が「もうだめなんだ」って思ってしまう
原因にもなってるかなと思います。
お母さんの自己肯定感がすごく大事
自己肯定感っていうのがすごく大事で、
お母さん自身も何が起きても
子どもが学校に行きたくないとか
なんか言ったとしても、
いちいち「私の子育てのせいか」とか
ビクビクせずに
起きたことは起きたことで動いていく
ということがすごく大事かなと思います。

家族療法の中でも
子どもが問題を出してくれることによって
家族の問題が解決するというのが
あります。
子どもが学校行きたくないとか
子どもがしゃべらなくなったりとか、
チックとか症状が出た時に
子育てのせいかって思いがちなのですが、
でもその症状を出してくれたことによって
家族がどう変わっていけるかっていう
チャンスでもあるので、
「そこからどうするか」ということを考えて
一緒にいけたらいいかなと
私は常に思ってます。
まとめ
「子どもの新学期どう見守るか」をテーマに
4・5・6月の流れをお話ししました。
4・5・6月は、
ゆっくりスタートしてあげて
親御さんも一喜一憂せず
こんな流れなんだっていうことを知って、
「日々がんばってるね」
という声かけしてもらえたら
嬉しいかなと思います。
今回は新学期バージョンでお話ししましたが、
「通年であったら嬉しい」っていうご意見を頂いたので
今後お話していきたいなと思っています。
中学校・小学校高学年の問題の多くは
今やSNSに移動していて、
学校ではあまりわからない
となってきてることが多いです。
LINEの中ですごく喧嘩があったりとか
グループを外したり外されたりとか
そういうことが起きてて、
実際に何が起きてるのかっていうのが
ちょっとよくわからない学校だけでは
というのがすごく多いです。
そういったことも、
またお話しできたらなと思います。